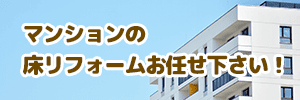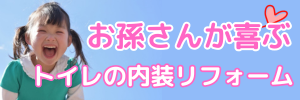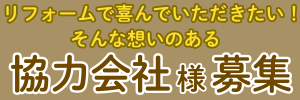床下点検口を作りたい!作れない場所ってあるの?
今回は、必要に応じて床下点検口が必要になったという方向けにお話しさせていただこうと思います。
例えば「床下の状態を正確に把握したい」「床下から床の断熱工事をする」「床下の配管の水漏れ補修を行う」など、状況によっては床下点検口がなければ「できない」ようなことってあるんですよね。

その際に、床ぷろにも床下点検口の新規設置をご依頼いただくことも多いのですが「どこに床下点検口を設置するのか」ってかなり重要なんですよね。
まず一つ目に覚えておいていただきたいのはお住まいの構造を傷つけてしまうような場所は開口できないということです。

床下の場合であれば、床を支える大引きや束を切ってしまうようなことはやってはいけません。
当然そうした構造部を切断なんかしてしまえば、床自体を支えられなくなってしまうため建物が傾いたり、床が抜けたりといった事態になりかねません。
次は目的に応じて場所を選定するということですね。
やたらめったら、どこでもいいというわけにはいきませんよね。床を開けてしまうわけですから、いくらそこに蓋を付けるからといってもこれまでと見た目も歩き心地も違いがあります。

特に歩行場所に床下点検口を作った場合、床の上を歩いているのとは少し違いますね。
ですから例えば床下を一時的に確認するような場合であれば和室の畳の下でもいいですよね。必要なくなれば畳を乗せれば隠せますので。
ただ逆に床下の配管を補修するような場合は、開口後多少床に違和感を感じても、配管に近い位置を開けなければ作業ができません。この場合は見た目よりも、補修を優先しなくてはいけませんね。このように目的に応じて場所を選定するということですね。
では、どれくらいの大きさの点検口を作ったらいいのか?ということですがサイズは450mm×450mmか600mm×600mmの二択になります。(このサイズであれば既製品の枠が販売されているので費用を抑えて床下点検口の新設が可能です)
もし人が出入りするのであれば600mm×600mmが望ましいです。
あとは床下点検口でいいのか?少し費用をかけて床下収納庫にしてしまうのか?この辺りも検討しておくとよいですね。(ちなみに床下点検口を後から床下収納庫にすることは容易ではありません→これについては以前のブログ「床下点検口は床下収納庫にできる?」をご覧ください)
床下点検口がいきなり必要になってしまった!そんな方はぜひ参考になさってくださいね!

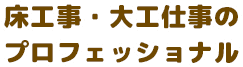
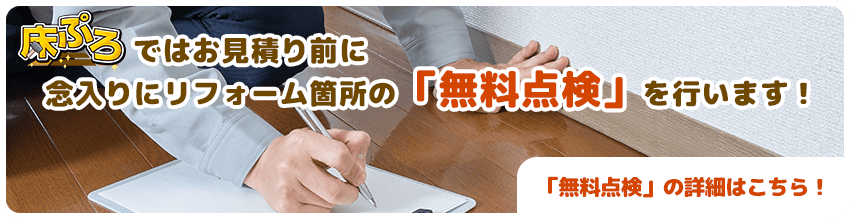
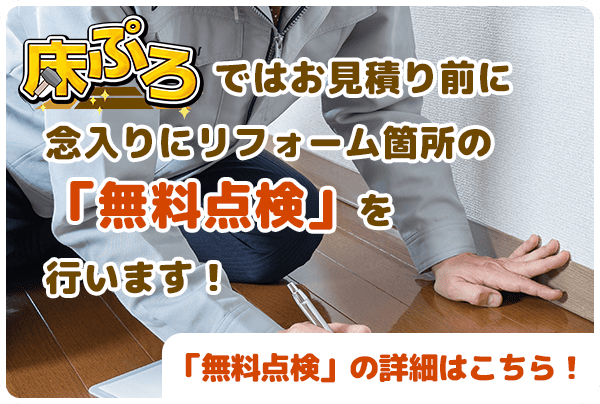
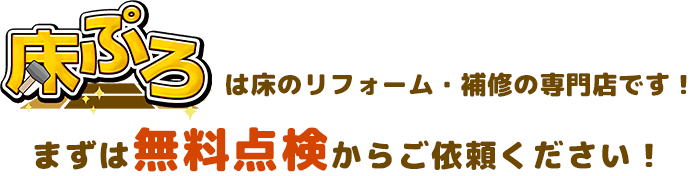
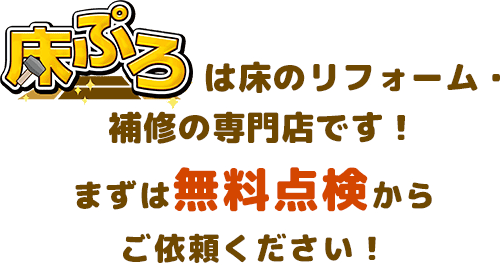
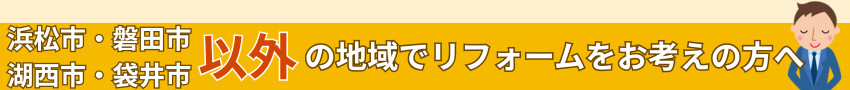
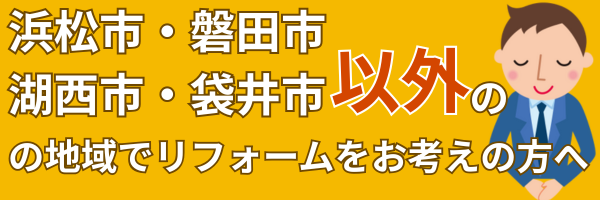
 施工事例
施工事例
 お客様の声
お客様の声
 現場ブログ
現場ブログ