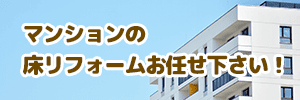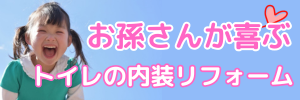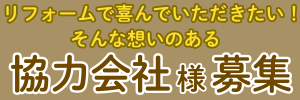床下の湿気対策|調湿材と防湿シートの違いとメリット・デメリット
地面の土壌がむき出しになっている布基礎の建物において床下の湿気対策は、住宅の耐久性を保つために欠かせません。湿気がこもると、木材の腐食やカビ、シロアリ被害の原因となってしまいますからね。
そんな床下の大敵である湿気対策として、「調湿材」と「防湿シート」による対策がありますが一見どちらも似たような言葉ですから、何がどう違うの?と疑問に思う方も多いのではないでしょうか?実は全く別の対策なのですが、今回はこの調湿材と防湿シートについてそれぞれの特徴やメリット・デメリットについて解説していきたいと思います。
調湿材とは?

調湿材は、床下の湿気を吸収・放出して湿度を調整するもので、施工としては基礎の土の上に小石状の調湿材を撒くような形となります。(袋のまま敷き詰めるタイプのものもあります)
調湿材の特徴としては、湿気が多い状況下では湿気を吸収、そして湿気が少ないときには放出するという特性があるため床下の湿度を一定に保つことが可能です。
また湿度が気になる場所に局所的に施工ができるため、基礎全体に施工が必要な防湿シートと比較すると施工が容易で、費用も抑えることが可能です。
すでに湿気に悩まされている場合の問題解決策として有効です。同様の対策としては床下換気扇の設置が考えられますね。
防湿シートとは?

防湿シートは、床下の地面からの湿気を遮断してくれるシートです。
床下の湿気は地面(土壌)から上がってくるため、厚さでいうと0.1mm程度の防湿シートという蓋をしてしまうことで地面からの湿気をシャットアウトするというわけですね。
湿気問題を根本的に解決したいという場合に向いている方法と言えます。
ただ一部のみに防湿シートを敷くということでは意味がないため、お住まいの床下全体に敷設する必要があるため調湿材と比較すると費用も少し高くなります。
お住まいの状況によって、できるできないがあるため事前の現地調査が欠かせません。
今回は調湿材と防湿シートについて説明しましたが床下の換気対策としては床下換気扇の設置や換気口の設置など様々あります。
お住まいの状況、立地場所等、千差万別のため一つの湿気対策だけではなく、複数の対策を実施したりとお住まいによって様々です。
効果的な湿気対策にするために床ぷろではまず現地調査で、現状を確認させていただいた上で必要な対策のご提案とお見積りを作成しておりますので床下の湿気が心配という方はまずはお気軽にご相談くださいね!

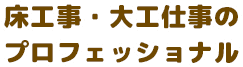
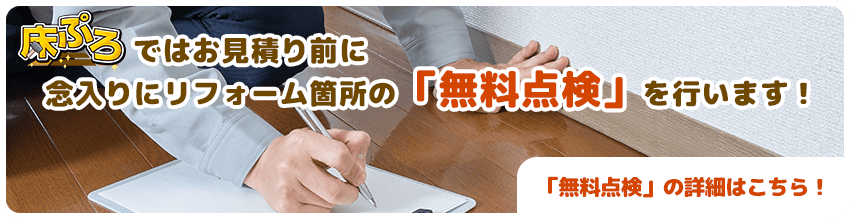
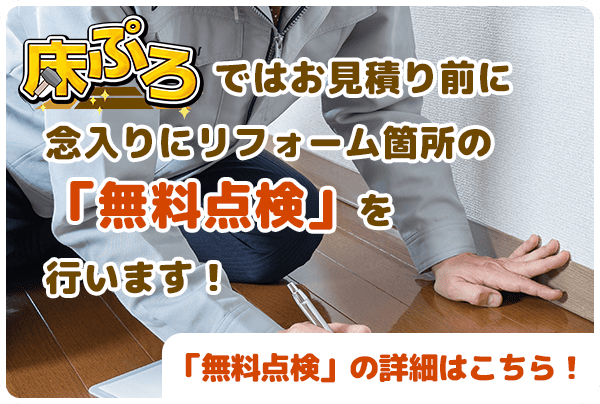
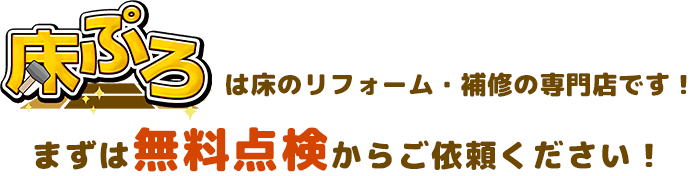
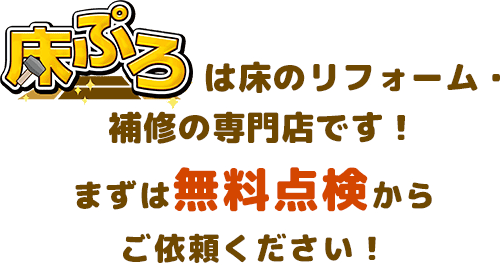
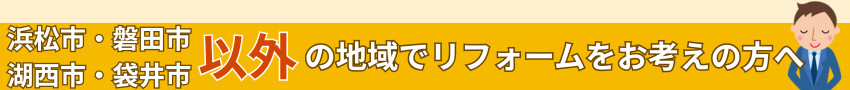
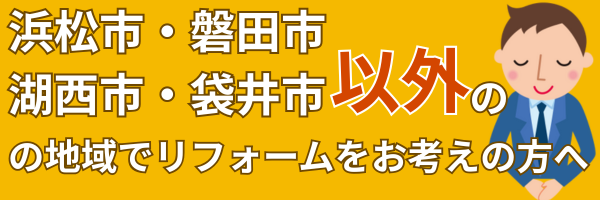
 施工事例
施工事例
 お客様の声
お客様の声
 現場ブログ
現場ブログ