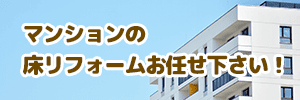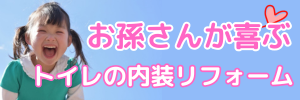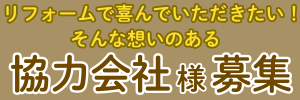根太張り工法で仕上げた床の浮きはフローリング材が原因?
根太張り工法というもの自体がよくわからないという方も多いですよね。
以下は床の内部の構造ですが、フローリングを解体した内側の構造(床組み)は実はこのようになっています。

一番上側に等間隔(303mmピッチ)で配置されているのが根太(ねだ)、そしてその下には大引き(おおびき)と呼ばれる一回り太い角材があり根太を支えています。
根太張り工法というのは、この303mm間隔で配置された根太の上に直接フローリング材を貼っていく工法となります。
根太や大引きがあるとはいえ、空間部分はフローリング材のみで重量を支えることになるため、床の強度という部分でデメリットもある工法ですが、築年数の古い一昔前の建物はこのような工法でフローリングを施工していたのが一般的でした。
(※現在は捨て貼り工法といって、根太の上に一枚下地となる12mmの合板を張って、その上にフローリング材を固定するのが一般的な工法となっています)
根太張り工法の床鳴りの原因は?
床の浮きの原因自体は大きく分けて3つあるのですが、
1.フローリング材の接着剤の剥がれによるもの(複合フローリングの場合)
2.下地合板の接着剤の剥がれによるもの
3.束石と束の間に空間ができてしまったことによるもの
ですが、根太張り工法の場合、2はないので1か3に限定されます。今回はフローリング材が原因と仮定してお話したいのですが、どういうことかというと、(以下の写真をご覧ください)

複合フローリングという建材は、いくつかの素材を接着剤で固定して、層を形成しています。
つまり接着剤が剥がれることによって、層と層が剥がれてしまいフローリングが浮いてしまう、またそこを踏むとぶかぶかするような感触を感じるのです。
もちろん根太張り工法に限らず、捨て貼り工法でも同様のことが原因で床が浮いてしまうことがあります。特に家族みんなが同じ場所に立つような、例えば洗面台の前、浴室の出入り口、玄関などは他の場所よりも日頃からストレスがかかっているためどうしてもこのような劣化が進みやすい場所と言えます。
もしこのような浮きが現れてしまった場合、フローリングの部分的な交換、また重ね張りなどによって解消することができます。浮きが気になる、ぶかぶかした感触が気持ち悪いという方はお気軽に床ぷろまでご相談ください。

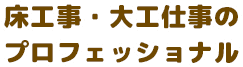
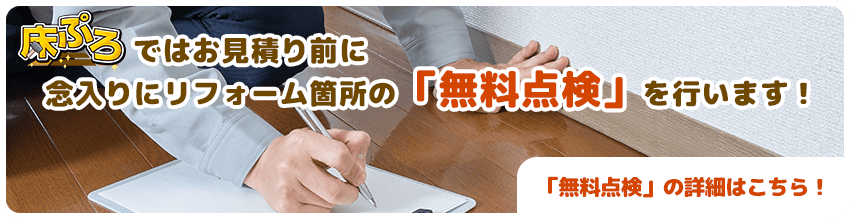
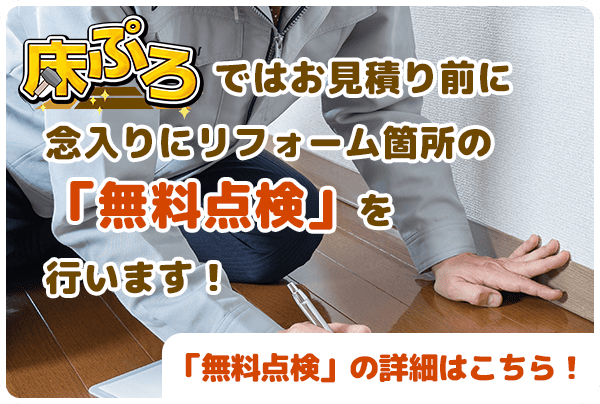
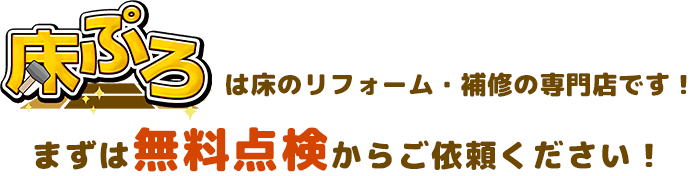
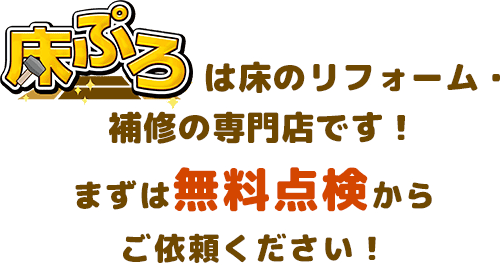
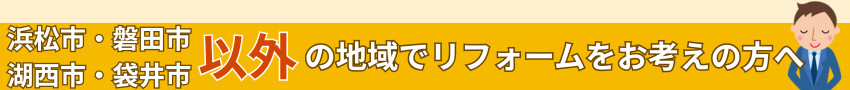
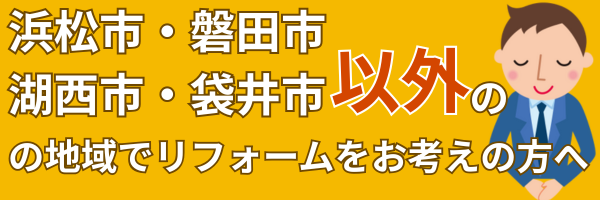
 施工事例
施工事例
 お客様の声
お客様の声
 現場ブログ
現場ブログ