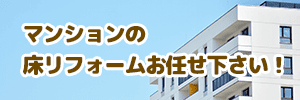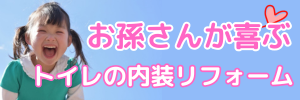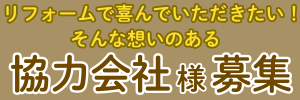室内壁の内部はどうなってる?【部位・用語解説】
断熱工事ということで床以外にも天井や壁の断熱工事もお任せいただくことの多い床ぷろですが、表面から見えているクロスはどうなっているのかという構造部分を見たことある方は少ないかもしれませんね。本日は室内壁の内部構造について部位・用語解説をしていきたいと思います。

壁の内部はこのように碁盤上になっているのですが、角材がそれぞれ配置されています。いずれも壁を支える重要な役割を持つのですが、今回は柱・間柱・胴縁についてどんな役割があるのかも含めて解説していきたいと思います。
柱(はしら)
柱はほとんどの方が聞き覚えのある言葉かと思います。壁表面から見える部材で、最も太い角材が使用されています。柱の役割はなんと言っても建物全体の荷重を支え、さらに地震や台風などの風圧といった外部の圧力から建物を守るための重要部材で垂直に設置されています。建物の強度に直結する最重要部材と言っても過言ではありませんね。
間柱(まばしら)
柱の間に配置する小さめの柱というとイメージ付きやすいかもしれませんね。柱同様、垂直に配置されているものが間柱です。間柱があることによって柱と柱の間が補強され、且つ壁面を支えてくれる役割があります。柱ほど太い角材ではありませんが壁の安定性を確保するためには欠かせない存在と言えます。また以下に解説する胴縁を支える下地としても機能しています。
胴縁(どうぶち)
柱や間柱と交差するような恰好で水平に配置されている角材が胴縁です。こちらも壁の強度や仕上がりに影響を与える部材で、壁の下地となる石膏ボードや合板を固定する役割も持ちます。このように壁の内部は柱と交差する形で胴縁が入りされ格子状にすることで壁全体の安定性を高めているのです。
いかがでしたでしょうか?
室内壁の内部構造は、家の強度や快適性を支える縁の下の力持ちと言えますね。「柱」「胴縁」「間柱」といった部材がどのように機能しているかを知ることで、住宅への理解が深まります。是非参考になさってください!

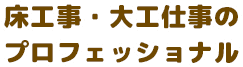
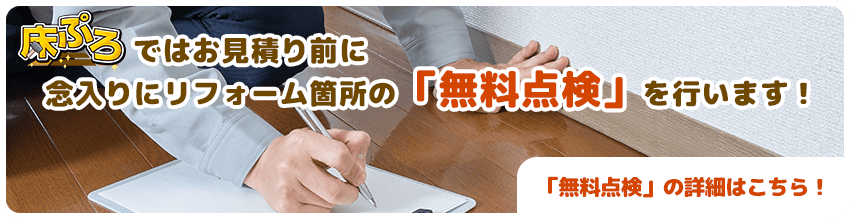
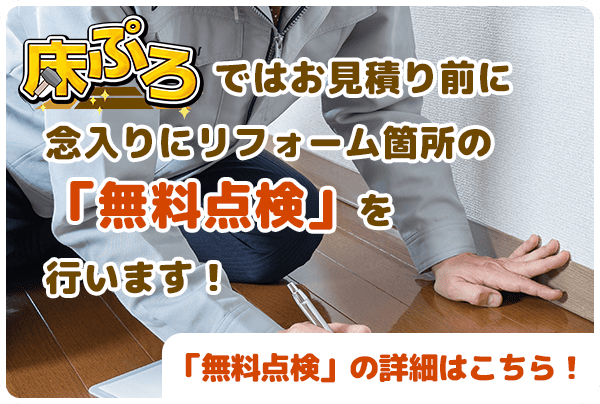
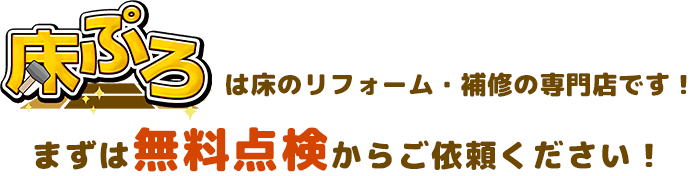
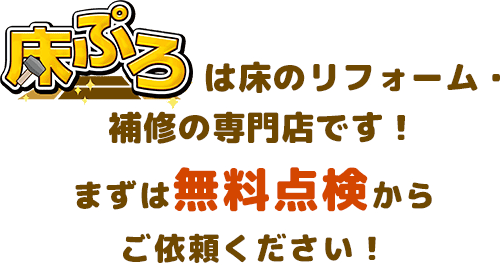
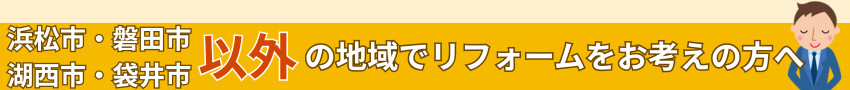
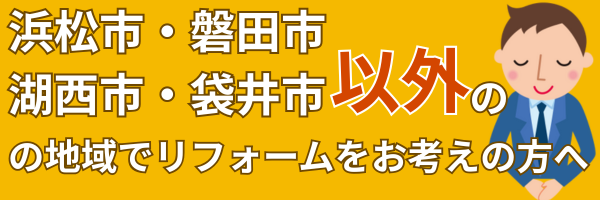
 施工事例
施工事例
 お客様の声
お客様の声
 現場ブログ
現場ブログ