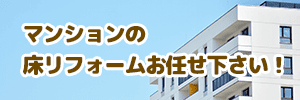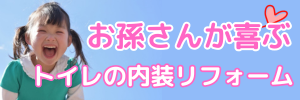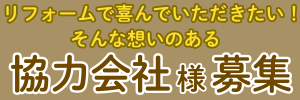天井裏・屋根裏の構造はどうなってる?【部位・用語解説】
断熱工事で床と併せて天井の断熱工事のご依頼をいただくことも多いのですが、天井が実際どうなっているか?ってなかなかわかりませんよね。上がってみればわかるのですが危険ですし、構造を見ても土の部材が何の役割を担っているのかって難しいもの。
そこで今回は天井裏(屋根裏)の構造についてそれぞれの部位の名称や役割などについて解説していきたいと思います。まずは天井裏のお写真をご覧ください。

天井裏に上ったことがある方でなければ、目にする機会もない場所だと思いますが木造住宅ではこのように様々な木材によって屋根や天井を支えています。では今回は屋根・天井を支える8個の部材についてそれぞれ説明していきたいと思います。
野地板(のじいた)
瓦やスレートなどといった屋根材を支える土台で、外側には防水紙(古いお住まいだと土が敷かれています)が貼られ、さらにその表面に屋根材が乗っています。面積の大きな合板が使われることが多いですが、その昔は写真のように杉板を何枚も並べる形が一般的でした。
垂木(たるき)
屋根の形状を支える骨組み部分で、野地板を固定するための下地材としても機能しています。野地板はこの垂木に釘やビスで固定されることで強度が増す形となります。
母屋(もや)
垂木を横方向に支える部材で、屋根全体の強度を高めます。屋根を支えている根幹的な部材なので強度が求められるのですが、屋根の重量に耐えられるよう垂木などよりも太い90mm×90mm程度の角材が一般的に使われます。
束(つか)
母屋と梁を接続するために垂直に伸びる部材です。屋根の安定性を確保すると同時に、天井裏の高さを調整する目的もあります。床下にも束がありますが、どちらも重要な部材で床や屋根の安定に寄与しています。
梁(はり)
梁については聞いたことがあるかたもいらっしゃるかもしれませんね。古民家などでは梁がむき出しになっている建物もあります。こちらは屋根の骨組みの中心的な役割をにらっているのですが、屋根の重量を支えているいわば大黒柱ともいうべき存在です。
吊木(つりき)
野縁を吊り下げて支えるための部材で、梁に固定されていることが多い部材です。吊木があることで屋根の平坦さや安定性がより保たれています。
野縁(のぶち)
天井板を固定するための部材で、天井の平面を形作るための基礎となります。格子状に組まれています。
天井板(てんじょういた)
室内から天井裏の構造を見えないようにするために貼られた部材です。ちなみに私たち業者が行う天井断熱とはこの天井板に断熱材を敷きこんでいく工事となります。
いかがでしたでしょうか。建築用語というとなかなか聞きなれないものも多いですよね。でもこういったことを少しでも知識で持っておくと業者との打ち合わせなどもスムーズに進むかもしれません。是非参考になさってくださいね。
天井断熱などに興味がある、少し考えているという方は床ぷろでは事前に調査をさせていただいた上で必要なお見積りをお出ししております。調査、お見積りは無料ですので是非無料点検をご活用ください。

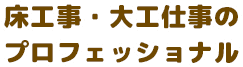
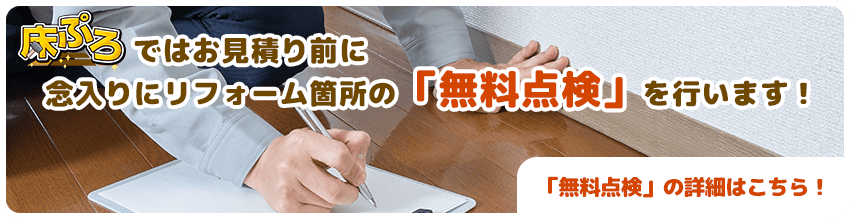
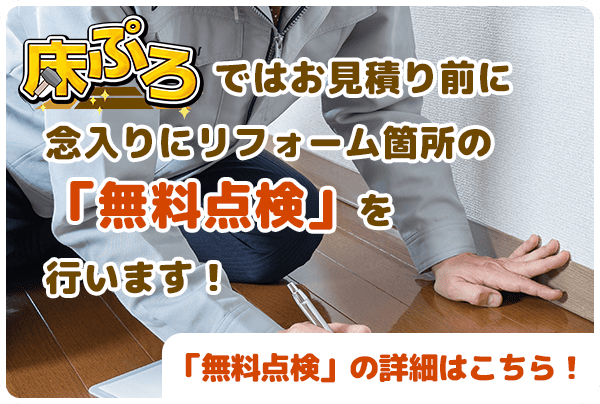
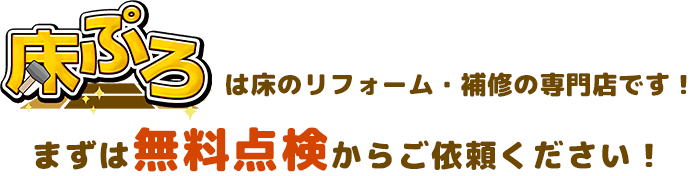
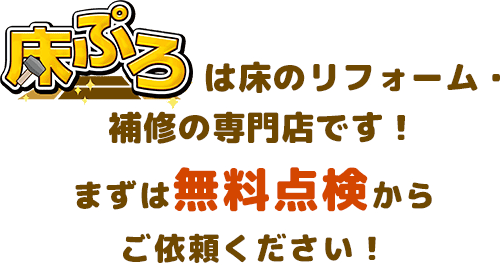
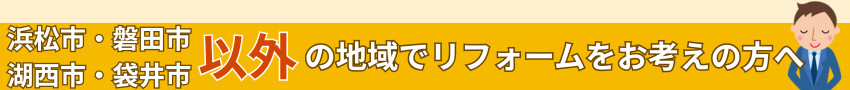
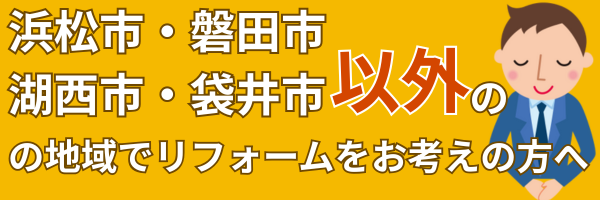
 施工事例
施工事例
 お客様の声
お客様の声
 現場ブログ
現場ブログ